| 胎便吸引症候群(たいべんきゅういんしょうこうぐん) |
正期産や過期産、不当軽量児などに起こる代表的な呼吸障害です。
赤ちゃんがお母さんの子宮の中にいるときに何らかの原因で低酸素状態になると、赤ちゃんの腸の動きが活発になりさらに肛門括約筋が緩むために胎児の腸の中にある胎便が羊水中に排泄されてしまいます。
さらに胎児が呼吸運動するとこの胎便で汚染された羊水を吸引してしまい、気道が胎便で汚れてしまい産まれた後で呼吸障害をおこしてしまいます。
分娩時に羊水が混濁していて、産まれた直後に新生児が元気が無いときには直ちに気管内吸引をおこないさらに呼吸状態が安定しないときには気管内挿管(きかんないそうかん)などの処置が必要です。 |
| |
|
| 胎便とは |
妊娠10〜16週頃から胎児の回腸で作られます。緑色をした液体状で、成分は胃や腸からの分泌物、胆汁や膵液、羊水中にある細胞の残渣・産毛・胎脂などです。 |
| |
|
| 頻度 |
胎便を混入した羊水は全分娩の14〜15%にみられ、その内の10%前後に胎便吸引症候群を起こすといわれています。赤ちゃんの死亡率も高く発祥したうちの12%とも言われています。
胎便混入羊水の発生頻度は早産児には比較的少なく、過期産児(予定日を超過したお産)に30%前後と多いようです。この理由として胎児の成長に伴い腸管の動きが活発になることが考えられています。 |
| |
|
| 原因 |
胎児が子宮内で急性や慢性を問わず、何らかの原因で低酸素状態(胎盤から酸素の供給が低下)になると、胎児の腸管の動きが活発になり、さらに肛門括約筋が緩んで胎便の羊水内への排泄(子宮の中で赤ちゃんがうんちをしてしまう)が起こります。
また一方、胎児は低酸素状態によって呼吸中枢が刺激されてあえぎ呼吸を始めるために(苦しくなって呼吸運動を始める)、胎便で汚染された羊水を吸い込んでしまうために起こります。
胎便の呼吸器へ対する影響
1) 胎便が気道につまって気道閉塞を起こす。この場合完全閉塞と一部気道を狭めてしまう不完全閉塞があります。
2) 胎便が化学的な肺炎を起こしてしまう。気管や肺自体に炎症変化を起こし組織破壊をおこす。
3) 胎便が肺サーファクタント(肺を膨らませるために必要な物質)を阻害して、肺の拡張を妨げ、さらに肺の血管を収縮させるため肺の血圧が上昇してしまう(肺高血圧症)。 |
| |
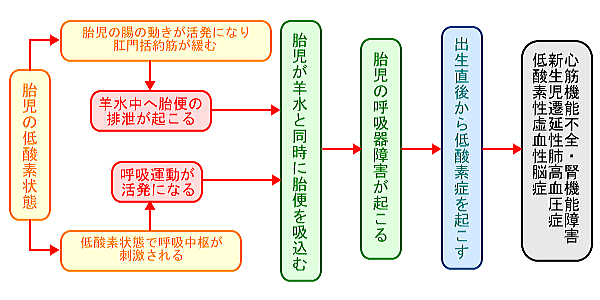 |
| 症状 |
分娩中は胎児の状態が安定せず、胎児仮死や分娩直後に新生児仮死を伴うことが多いです。子宮内で胎便を排泄した時期が古いときは羊水全体が黄色がかり、比較的早期では緑色です。また臍帯(へその緒)、胎児の皮膚、爪などが胎便によって染色されていることもあります。
呼吸状態は、呼吸窮迫(多呼吸・陥没呼吸・呻吟(しんぎん)・鼻翼呼吸・チアノーゼ)状態がみられ、聴診で肺全体にラ音と呼ばれる雑音が聴かれます。
通常では、数日以内に快方に向かい呼吸も安定してきます。しかし重症例では1〜2週間の呼吸管理が必要になることもあります。 |
| |
|
| 診断と治療 |
分娩時の状態や呼吸状態から診断されることがほとんどですが、赤ちゃんの胸部レントゲン撮影などで他の疾患や合併症を診断します。治療の基本は、呼吸管理と全身状態の管理維持です。
呼吸管理
必要に応じて人工呼吸器などによる人工換気を行います。さらに人工肺サーファクタントによる肺の洗浄や補充療法を行います。
全身管理
保温、血液中の電解質の補正やその他合併症の治療を行います。 |
| |
|
| その他の呼吸障害 |
詳しくは・・・→ こちらへ |